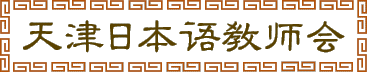 |
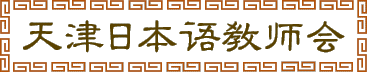 |
| 研究発表 |
*勉強会の報告と、会員の研究発表を掲載します。授業の準備などの参 |
|
17.第1回 河南省日本語スピーチコンテストの報告 川端 敦志 16.授業報告「五要十不」 斉藤 正 15.授業報告「終着駅は始発駅」 斉藤 正 14.授業報告「時間について考える」 斉藤 正 13.授業報告「会社人としてのあり方と私の会社生活」 斉藤 正 12.授業アイディア「考える遊び」 斉藤 正 11.授業の雰囲気を変えるちょっとしたネタ 細井 10.授業報告「日本の企業で働く場合に留意すべきこと」 斉藤 正 9.学生の作文の誤用例と国語辞書 足立 吉弘 8.私は感動されました 八尾 由子 7.「彼は毎日勉強しなくて遊んでばかりいます。」 吉永 里香 6.中国人学生への発音指導について 28回教師会グループ討論報告 5.生徒のやる気とプラス思考 剱持 昌宏 4.「ようだ・そうだ・みたいだ・らしい」 3.「うれしい・たのしい・よろこぶ」 2.「そこで・だから」 1.授業報告 永森久美江 |
| 戻る |
日本語教育関係者の皆様、はじめまして。 大会の流れ 第1部 テーマスピーチ 第2部 即席スピーチ 全体のテーマスピーチ:「私の目から見た日本」 |
| 戻る |
詳細はこちらをご覧下さい。 |
| 戻る |
詳細はこちらをご覧下さい。 |
| 戻る |
詳細はこちらをご覧下さい。 |
| 戻る |
詳細はこちらをご覧下さい。 |
| 戻る |
詳細はこちらをご覧下さい。 |
| 戻る |
「数字ゲーム」(と言って、実は聴解の練習になります。) |
| 戻る |
「模擬授業」報告 資料概要: |
| 戻る |
“ところへ”を使って書いた学生の例文。(大学2~3年生) 大辞林の説明 基礎日本語辞典(森田良行)の説明 [私の意見] |
| 戻る |
学生に、映画を見た感想を書かせたときに出てきた文です。複数の学生がこのように書いていました。正しくは、もちろん「感動しました」または「感動させられました」です。どうしてこのような形を使ったのでしょうか。 |
| 戻る |
初級の 学生にとって「~なくて」と「~ないで」の使い分けは、かなり難しいもののようです。が、これは表にすると、ぐっと分かりやすくなります。
Ⅰ.「ない」の前が動詞で、「て」が「原因・理由」を表す場合 Ⅱ.「ない」の前が動詞で、「て」が「Aをしない」「Bをする」を「結合」する Ⅲ.「ない」の前が名詞、形容詞(い形容詞)または形容動詞(な形容詞)で、「て」 Ⅳ.「ない」の前が名詞、形容詞(い形容詞)または形容動詞(な形容詞)で、「て」 この説明をした後に、以下の問題で確認すると良いと思われます。 〔問題〕下の( )の中から適当な方を選びなさい。 上記の誤用は、初級の学生ではなく、実は2年生の作文(宿題)の中に見られたものです。添削し返却した後、確認問題を解いて、再度提出してもらいました。それを見る限りは、理解できていたようです。が、かといって、もうマスターしたわけではないのは、皆さんもご経験済みかと思います。言葉というものは、こういう間違いを何度も繰り返して、ゆっくりゆっくり身につけていくもの。焦らず、気長に、学生の誤用と付き合っていくのも、言葉を教える教師の役割の一つなのでしょう。 参考文献:『月刊日本語』’96.10,アルク,46-47 |
|||||||||
| 戻る | |||||||||
わたしたちのグループでは 中国人学生の発音指導について話し合いました。 [1]の濁音の聞き取りに関しては、中級以上になっても、単語の知識として清濁の区別をしているだけで、耳で清濁を聞き分けられていないと思われる学習者も多い。中国語では清濁ではなく、有気か無気かによって意味の区別を付ける。一般に日本人が濁音としているz、d、gなどは中国では無気音、日本語では清音としているc、t、kなどは有気の音である。 |
| 戻る |
「やる気」とは何か?そしてそのやる気を維持する方法は? 本来、勉強とは楽しいもの。そう思いませんか。 それが何故、いつの間にそうでなくなってしまうのでしょうか。 勉強がさせられるもの、押しつけられるものになるからですよね。 常に、授業の始まる時にやりたいという気持ちを作ってしまう。それが一番大切なんです。本当は、授業のノウハウなんかよりもこれが一番大切なんです。 この授業は楽しいというイメージを作ってしまえばこっちのもの。 まあ、理屈はわかるけど現実はそうはいかないよ。やるのは勉強なんだよ。そう楽しいというイメージを簡単に持たせられるわけがない。という風に思う人もいるかもしれませんが、教える側が、そう思ったら、その気持ちは必ず学生に伝わります。人の気持ちというのは、言葉を越えて簡単に相手に伝わります。 特に、好き嫌いというのは簡単に相手に伝わります。教師として、一番してはいけないのは、嫌いな生徒を作ること。誰だって嫌いな生徒はいるでしょう。いても教師だから、絶対顔に出したり、言葉に出したりはしませんよ。という人がいるかもしれませんが、それは不可能。人間どんなに隠しても、ちょっとした表情に表れてしまうものです。こちらは気づかれているとは思っていなくても、相手も気づいていると思っていなくても、潜在意識が、お互いに嫌いと気づいてしまっている。 私も新人の頃は、苦手な学生がいました。ちょうど校内暴力が問題になっていた時期ですので、学校の中は常に一触即発の状態でした。廊下を歩いても、生徒と教員の間で、視線がぶつかり、火花が飛ぶような気がしました。こんな私ですが、昔は2回ほど、松の廊下の浅野匠守状態になったことがあります。そんな当時、私には一人の、本当にどう扱っていいかわからない女子生徒がいました。まあ、いわゆる女番というタイプの生徒でした。もちろん面と向かって、難しい生徒だなんていうわけもないのですが、いつの間にかこちらの態度で気づいてしまい、ますます難しくなってしまったという経験をしました。一年も相手をしていると、隠しきれるものではありません。一度女子生徒との関係を壊してしまうと修復はほとんど不可能に近いということも経験から学びました。 隠してもばれる。一度壊れた関係は修復不能。 では、どうするか。答えは簡単。 「こいつら、態度悪いなぁ。もっとしっかり聞けよ。」と思って授業をしている人の授業を学生が聞くわけがない。なぜなら、その教師の不快感が、学生に伝わっているからです。双方が不快な気持ちを抱えたまま、効率の悪い授業を続けているのは、労多くして益無しの典型です。時間が経つほど、つまらない授業になるでしょう。 話を元に戻しますが、授業を受けたい、勉強したいと思わせるには、教師自身が 右脳と左脳の話を聞いたことありますか。右脳は、感覚的な世界を司り、左脳は理論的な思考を担当する。…そうです。そして、その人、その授業に対するイメージは右脳が作るんです。理屈じゃないんです。感覚の問題なんです。右脳の働き、右脳の記憶力というのは大変速くて、優秀なんです。スポーツの世界では、この右脳の働きを競技に生かせないかと随分研究が進んでいます。 随分長い横道にそれましたが、これを授業に活かすのは実は簡単なんです。 まず (例)私の授業の入り方(具体的に) とにかく一番大切なのは「笑顔」です。最初は学生も戸惑うかもしれませんが、それでも続ければ、だんだん教師に対するイメージが変わってきます。どの学生と会っても、心からの笑顔であいさつをしてくれるようになったら大成功です。 またまた、当たり前なことをいっていると思うかもしれませんが、科学的にもこの笑顔の効用についてはだいぶ研究が進んでいます。 ・笑顔を作ると(無理矢理でも何でも)、脳に今この人は笑顔だという情報が送られ ※野球の世界では、試合中に笑顔でプレーするということを勧める指導者が急増している。ちょっと前まで試合中に笑うなんて不謹慎だと、監督にぶん殴られていたのにですよ。一にも二にもそれは、選手が力を出すためにはどうすればよいかを考えてのことです。一時期日本のスポーツ選手が、大きな試合に弱いのは何故かと盛んにいわれた時代があります。今、大切な試合、大きな舞台で活躍する日本人選手が増えています。その違いは何か?それは「笑顔」とプラス思考だと思います。メンタルトレーニングと言いかえてもいいかもしれません。 授業も一緒です。教師が楽しく話していれば、その楽しさは学生にも伝わります。一に笑顔、二に笑顔、三四も笑顔で、五も笑顔。これで行きましょう。 プラス思考の話も少ししておきましょう。 「脳内革命」お読みになりましたか。明るく楽しく前向きな気持ちになっていると、右脳からドーパミンというホルモンが分泌されて、いつも以上の力を発揮できるという内容のものです。 人間の能力というのは、なかなかたいしたもので、ほとんどの人はその持っている能力の大部分をつかわないまま一生を終えるといわれています。 火事場の馬鹿力という言葉もありますね。あれはない力が、出るのではなく、普段出せない潜在能力を引き出したということなんですよね。そうとわかれば、その馬鹿力を出したい時に出せるようになればと考えるのが当然ですよね。その鍵を握っているのがプラス思考なんです。 これは、何も筋力だけの話ではないのですよ。笑顔とプラス思考は、潜在能力を引き出す最大の武器なのです。 では、辛い時、苦しい時、そんなときにどうすればプラス思考をすることが出来、自分の実力を出し切ることが出来るかというとについてお話ししましょう。 その鍵は、自己暗示なんです。どんな自己暗示かというと、どんなときも何が起こっても「自分はついている」と暗示を掛けること。そうすれば、物事をプラスに考えられるようになります。 (例1)考えてもいなかった海外単身赴任。 (例2)一番やりたくない授業をやることになった。 (例3)日本代表をはずされた中村選手の場合。 まぁ、基本はいつでも「ついている」と思うことです。そして、その理由付けがうまくいけばいくほど、効果は大きなものになります。何故、ついているのかという理由付けですよね。普通の人が、ついていないと思えるようなことが、ついていると心の底から思えるようになれば、あなたもプラス思考の達人ですよ。 いいですか、くどいようですが、一番大切なのは 「笑顔」と、「プラスの自己暗示」です。 これで、生徒のやる気も維持され、教師のやる気もでるというものです。 |
| 戻る |
①「ようだ」と「みたいだ」 「ようだ」 改まった話し言葉・書き言葉 によく使う。 ②推量をあらわすことばと、そのニュアンス 《比較》 ③伝聞をあらわすことばと、そのニュアンス 《比較》 ~久下先生より追記~ 四 次の2~5は、1の「~だろう」の言い方と比べて、どう違うか、考えなさい。 五 次の1と2の「そうだ」は、どのように意味が違うか、考えなさい。 六 次に示す1~4の文は、それぞれ、どのように意味が違うか、考えなさい。 その他 ついでに、 |
| 戻る |
①「うれしい・たのしい」と「よろこぶ」 1.「うれしい・たのしい」は形容詞 で、「よろこぶ」は動詞 2.「よろこぶ」は、話し手や聞き手が主語のとき、一般的には使わない 3.「うれしい・たのしい」は、第三人称が主語のとき「~そうだ」をつける ②「うれしい」と「たのしい」 1.「うれしい」・・・主語に直接関係のある、個人的で具体的な理由があるとき (例)うれしい話:その内容が、「主語」個人に関係があることで、それを知 |
| 戻る |
①「そこで」・・・原因―結果の関係がなくてもいい。 ②使い方 (例)この家は安い。(×そこで ○だから)私でも買える。 |
| 戻る |
授業で心がけたこと 毎時間、時間の最初にやったこと ① ニュースや日本の様子の書き取り 授業の内容 ① 日本の食費を考える ② 仕事について考える ③ 住居費について考える ①.②.③.のことを取り入れたのは日本に留学したいという学生がとても多いので、日本の生活について現実的なことを考えたほうが良いと思ったからです。この授業を通して、「結婚のとき男の親が家を買ってくれることが多い」など、中国の風習がわかったのですが、丸抱えで親に依存して、自分では、大して勉強しない、学生に「これでは親がかわいそう」という思いを強く持ちました。 ④「家族の会話」を作り、グループで演じる授業 この授業の良かった点 困った点 ⑤スピーチの授業 数え方の暗記 書き取りテスト ディベート(討論) その他努力したこと |
| 戻る |